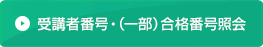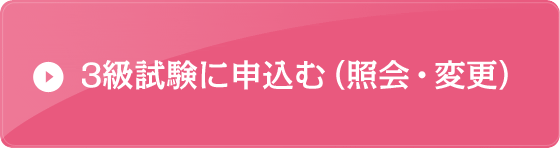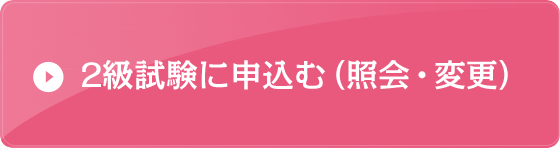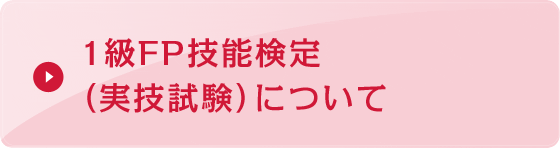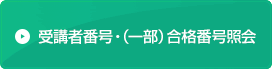2級FP技能検定に関するよくある質問
-
Q1
学科のみ・実技のみ受検したい
A1可能です。受検申請時にご選択ください。
一部合格している場合には免除申請をしてください。詳しくは以下よりご確認ください。 -
Q2
金融財政事情研究会で3級合格後、2級を日本FP協会で受検したい
A2可能です。日本FP協会での受検申請時に、3級の合格番号を記載してください。合格番号が不明な場合は、金融財政事情研究会へお問い合わせください。
-
Q3
金融財政事情研究会で一部合格後、日本FP協会で受検したい
A3可能です。日本FP協会での受検申請時に、一部合格番号を記載してください。一部合格番号が不明な場合は、金融財政事情研究会へお問い合わせください。
免除申請について詳しくは以下よりご確認ください。 -
Q4
バリアフリー対応(設備・座席の配慮)を希望する
A4以下より手続きを確認のうえ、期日までに申請してください。
-
Q5
合格番号・一部合格番号が知りたい
A5日本FP協会で合格した場合は、以下より照会できます。
受講者番号・技能検定(一部)合格番号照会のご案内
該当がない場合は金融財政事情研究会で合格している可能性があります。 -
Q6
AFP認定研修の受講者番号が知りたい
A6以下より照会できます。
-
Q7
業務内容が実務経験に該当するか確認したい
A7実務経験については、自己申告ですのでご自身でご判断ください。受検資格の可否に関するお問い合わせには回答できません。詳しくは以下よりご確認ください。
-
Q8
受検申請画面がフリーズした
A8問合せ番号がお分かりの場合、ログインして再開してください。
支払いが完了していない場合、再度、申請し直すことも可能です。 -
Q9
受検申請後のメールが届かない
A9メールの再送はできません。問合せ番号がお分かりの場合、申請画面から申請状況やメールアドレスをご確認ください。
-
Q10
コンビニエンスストアでの支払期限を過ぎてしまった
A10申請は自動キャンセルとなります。期限後のお支払いはできません。
-
Q11
支払いしたのにキャンセルのメールが届いた
A112回以上申請をされている場合、問合せ番号をご確認ください。
申請完了している問合せ番号と、キャンセルメールに記載の問合せ番号が異なっていれば問題ありません。 -
Q12
受検申請内容を変更したい
A12以下より手続きを確認のうえ、期日までに変更手続きをしてください。
-
Q13
受検票が届かない・紛失した
A13インターネット申請の場合、申請画面から受検票の再発行が可能です。開始日時等を以下より確認のうえ手続きをしてください。
-
Q14
試験会場がわからない
A14インターネット申請の場合、受検票の再発行が申請画面から可能です。開始日時等を以下より確認のうえ手続きをしてください。
受検票 -
Q15
持参できる本人確認書類について
A15以下よりご確認ください。
試験当日
※「本人確認書類」の項目をご確認ください。 -
Q16
遅刻について
A16試験開始より30分までは入室できます。公共交通機関による遅延の場合は試験開始後1時間まで入室できます。
-
Q17
欠席について
A17欠席連絡は必要ありません。結果通知には「欠席」と記載されます。
-
Q18
結果通知が届かない
A18以下よりご確認ください。
-
Q19
学科と実技を合格したのに合格証書が発行されない
A19受検申請時に免除申請をしていない場合、手続きが必要です。以下よりご確認ください。
-
Q20
一部合格の有効期限を知りたい
A20合格日の翌々年度末まで有効です。
免除申請について詳しくは以下よりご確認ください。